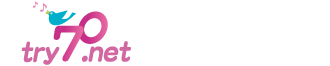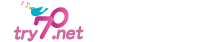はい、深く息を吸って
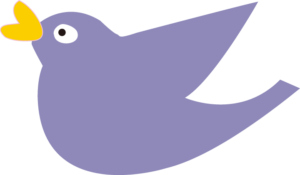
![]() はい、深く息を吸って
はい、深く息を吸って
「気功って呼吸ですよね?どんなふうに吸ったり吐いたりするの?」。気功をみなさんと始めたばかりの頃に、しょっぱなに受けた質問です。
いやいや、それはネ…、初めから呼吸を考えたら、そっちに気をとられて気功の動作ができないですよ。
「最初は呼吸を考えずに動いてね、慣れてきたら呼吸法をやりますから」。
とか何とか、私自身が師匠からいわれたそのままを答えましたが、冷や汗もの。
いまなら言えます、気功で呼吸はとても大事です。
気功には三調、或いは五調といった基本的な鍛錬方法があります。
「調体」(動作の調節)、「調息」(呼吸の調節)、「調心」(意念の調節)ここまでが三調。
これに加えて、「調気」(気感の調節)、「調音」(音声の調節)。これで五調。
三調、五調の1つ1つに中国数千年の気功の歴史が詰まっていて、それぞれにいくつもの鍛錬方法があります。…ああ、気が遠くなる。
詳しい説明をすると日が暮れてしまうので、とりあえず気功の鍛錬には、呼吸法だけではなくいろいろな分野があるということだけ理解してくださいな。
さて、呼吸は上記の三調、五調の中の「調息」ですね。でも、なぜ呼吸がそんなに重要なのか?
気功のおおもとは“気”です。
呼吸と“気”とは密接な関係にあります。
「天気通於肺(天の気は肺に通じる)」。
古代の中国人には酸素とか二酸化炭素という概念はありませんでしたから、呼吸によって自然界の清気を吸い込み、体内の濁気を吐き出して、気の生成を促し、新陳代謝を行っている、と考えました。
現代の研究でも、呼吸で自律神経系統の交感神経、副交感神経の調節ができ、ひいては内臓組織や器官を調節する機能がある、といいますね。
単なるガス交換だけではない効用がある。
緊張している、不安でドキドキしている時に深呼吸をするでしょ?あれは、自律神経のバランスをとって緊張を緩めているのですね。
五臓六腑の中で、肺だけが自分でコントロールすることができます。だから呼吸を操作することで、気を操ることができる、と考えたわけです。
気功は、大きくは静功と動功に分けられます。
静功といって動かない座禅では、呼吸とともに気を体内でまわしています。
気功の座禅は、仏教の座禅のように何も考えずに“空”になるのではなく、気を背骨から上に昇らせ、額にある上丹田からまっすぐ下に降ろして、体内で気をぐるぐる周回させています。
「小周天」という修行です。
動功といって動く気功でも、呼吸に法則があります。
重いものを持ち上げたり、夢中になっているときには無意識に息を止めていることが多いですが、これは“気をためている”状態。
気功ではいつも気を流しているので、息を止めないでゆっくり呼吸を続けます。
体を伸ばすときには息を吐く。息を吐いている時には体の力が抜けています。力が入りません。
いつも肩に力が入って緊張が抜けない人は、息を吐きながら肩を思い切り下に下げてみてください。
楽になりましたか?
ここで呼吸法の説明を。
3番目の「胎息(へそ呼吸)」こそが、気功のめざすところです。
1) まず、胸式呼吸法。自然呼吸ですね。
意識せずに息をしていると胸の呼吸になりますよね。
ラクですが、我々の年代になると胸の呼吸はだんだん息が浅くなって、口で呼吸するようになってしまう。
要注意、です。
2)次が、腹式呼吸法。これは少し訓練が必要です。
赤ちゃんを観察すると、お腹で呼吸していることがわかります。腹式呼吸は、赤ちゃんの呼吸。
おへその下まで息を吸いこむとお腹が自然に膨らむ。これをゆっくり吐いていきます。
逆腹式呼吸もあって、息を吐くときにお腹が膨らむ。
これにはまた別の効能があるようです。
腹式呼吸は、次の胎息(丹田呼吸)への第一歩です。
3)最後に、胎息。へそ(丹田)呼吸法です。
中国古代医学には、先天と後天という考え方がありますが、生まれる前の胎児の状態が先天。後天というのは生まれてから獲得したもの。
この先天の呼吸が胎息というわけで、胎児のときの肺も胃も使わないシステムを取り戻すことを目指します。
胎息の訓練方法
最初からへそ呼吸に突入するのではなく、順番があります。
まず手の平で呼吸することから始まって、足の裏、背中側、お腹側、皮膚全体、最後におへその奥の胎息(丹田呼吸)まで進みます。
1つができてから次に進むので、それぞれに1~2か月かけて、真面目に鍛錬して1年はかかる?!
でも、へそ呼吸5分で元気になる。
胎息によって遺伝子を変える、本能の力がよみがえる仙人になる。私の師匠は「胎息」ができれば“運命を変えることができる”といいます。
※私が思うに、運命とは生まれつき自分の体と心が持っている寿命、とでもいえばよいでしょうか。
胎息で、最終的には脈がコントロールできるそうです。師匠は脈を速くしたり遅くしたり、自由自在!!なんですもの。
呼吸法もいろいろ。体質が違う人のそれぞれの呼吸法もあります。
息を吸ったり(吸)、吐いたり(呼)、止めたり(停)、
の組み合わせです。鼻で吸い込み、鼻または口から吐く。苦しいと自律神経が乱れるので、楽に呼吸すること。呼・吸・停の長さはそれぞれ3つ数えるくらい。
【1】 吸・停・呼
体を暖めるパワーが不足して冷える人=陽虚
(舌が白っぽい、手足が冷える、頻尿、小便に色がなく多量、軟便etc.)
【2】 吸・呼・停
水分や血液などの体の陰液が不足して過熱状態の人=陰虚
(熱っぽい、肌が乾燥、便秘気味、咽や口が乾燥する、不眠、手の平や足裏が暑いetc.)
【3】吸・停・吸・呼
気を上にあげて昇陽に働くので、低血圧の人に。
まあ、あまり症状に拘らずに、自分が気持ちよい呼吸法を選べばよいのです。自律神経を調節するので、疲れがとれますから。
付録:風呼吸法(郭林気功)
郭林女史がアメリカにいたときに末期ガンになり、中国に帰国してから気功で治ったというもの。
一時期(1970年代)にずいぶん流行りました。
実は「風呼吸」といって昔からある気功の呼吸法。
強い呼吸で一気に体内環境を変えてしまう。
スッスッハー、と鼻から強く吸って口からはく。
歩きながら、手の平を下にしておへその丹田のところで左右に振りながらやります。
ネットで検索すると出ていると思います。
いろいろ書きましたが、とりあえず、私たちは腹式呼吸から挑戦するのはどうでしょう?深い息ができますよ。

国際中医師 国際医学気功師、国際中医薬膳師。
50カラット会議時代から週1回私たちに気功指南して、現在は水曜日10時からオンライン講座がある。