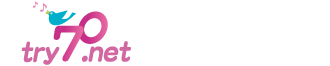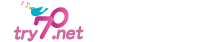わが家は犬。人間関係も穏やかな触れ合いに
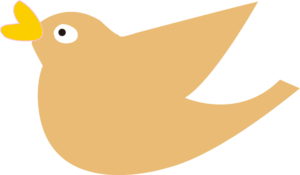
![]() わが家は犬。人間関係も穏やかな触れ合いに
わが家は犬。人間関係も穏やかな触れ合いに
アニマルセラピー
アニマルセラピーという言葉や内容を現在では知らない人はほとんどいないと思いますが、私が研究対象の一つに取り上げたいと思った30年ほど前には一般には余り知られていませんでした。
はじめに文献を読むと、アニマルセラピーは、Animal Assisted Therapy(AAT)とAnimal Assisted Activity(AAA)に分けて考えられるとされていました。
AATは動物介在療法と訳され、AAAは動物介在活動と訳されていました。つまりAATは代替医療の一つとして治療として行われるもので、計画的に動物を介在させて結果としてのエビデンスも見出そうとするものです。AAAは動物介在活動と訳し動物とのふれあいによって癒しを得たり、生活の質QOLを高めたりを目的とする活動としています。
この分類は現在も変わりませんが、以前はAATに求められた科学的証明(何らかの数値や計測可能な行動の変化等)は現代ではAAAでも得られることが実証されています。
動物と触れ合うことで幸せホルモンと言われるオキシトシンの分泌が促されることや喜びや快楽に関係するドーパミンや感情をコントロールさせ精神を安定させる働きをする神経伝達物質のセロトニンの生成などが実証されていますので、実際には両者の違いはほとんどないと言えるかもしれません。
要するに両者を総合してアニマルセラピーとして良いと思います。
ですからアニマルセラピーとは、動物と関わることによって、ストレスが軽減したり、心が穏やかになったりして簡単に言えば癒しを得られること、それによって心身の問題が好転することといえるでしょう。
米国での見学旅行
私がアニマルセラピーの実際を知りたいと調査を始めた頃メディアでアニマルセラピーについて記事を載せていた米国の人と知り合い、米国の実情を視察に行こうと誘われて行くことになりました。
まず彼女の紹介でその当時イルカセラピーの実践で有名だったベッツィ・スミス博士をマイアミのご自宅に訪ねました。
ところがその時には博士はすでにイルカを介在させるセラピーに疑問を持っていて実践から退いていました。
理由はイルカセラピーが人間のためになることは明らかだがイルカを介在させることによるイルカのストレスに問題を感じたからであり、その代わりとして人間と一緒に行動することを喜びと感じていると言われている犬の介在の方が問題が少ないという結論を得たからだということでした。
ただ、フロリダのキーラゴでイルカを介在させて組織的に行動療法を実践しているネイサンソン博士を紹介してくださいました。
そこでは脳性麻痺等で手足の働きがうまくいかない子供たちにイルカとともにラグーンに入りトレーナーが段階的にイルカと触れ合う時間を増やしてそれを報酬として運動量を獲得させる行動療法を実践しており、世界各国から子どもたちが治療のためにやってきていました。その実践を見学して地道な治療法であり効果をあげていることを見学させていただき、お話も伺うことができました。
その当時の典型的なAATであると実感できた体験でした。
その後フロリダ半島最先端のキーウエストでヘミングウエイの住まいを見学してそこにしかいない6本指のねこちゃんたちと会いました。それらの猫によってヘミングウエイも癒されていたようです。
その後北部へ戻ってホースセラピーの見学もしました。ここでは障害のある方たちが乗馬をすることによってリハビリを行っていました。
乗馬で腿の内側で馬の胴体を挟むことで体を支える事の効果や馬の歩行の揺れが人の歩行の動きと連動するとのことでリハビリ効果などの説明も受けました。実際に障害のある方たちの回復のプロセスも目の当たりにしある意味でのアニマルセラピーを実感しました。
その後、ニューヨーク郊外のサミュエル・ロス博士によって1947年に設立された「グリンチムニーズ」へ泊りがけで見学にいきました。
ここはアニマルセラピーを中心に情緒障害や虐待にあった子供たち、家庭の問題や学校教育になじめない子どもたちを対象にした寄宿制の療養施設です。
馬をはじめとする動物やけがをした鳥(フクロウやタカなども)や小動物の世話をしたり介護したり一緒に過ごすことでの心のケアを目指しています。医師、看護師、心理学者、ソーシャルワーカー、教師、動物の専門家、などの多くのスタッフが子供たちをサポートしています。
ここでは教室に放し飼いにしたフクロウがいたり、小動物のケージがあったり、校内を馬車に乗って子供たちが移動したりしています。
馬車を引いている馬は大きなペルシュロン種の白馬で、ディズニーランドで馬車を引いていてその後引退した馬だそうで、動物たちの新たな居場所作りや介護にも力を注いでいるとのことでした。
ここでのアニマルセラピーは多岐にわたりますが、傷ついたタカを心が傷ついた子どもが心理学者と一緒に行動療法によるリハビリに取り組みタカを野生に返すことに成功しそれによって子ども自身もこころの傷から回復したビデオなどもみました。(このビデオは後に日本でも放映されました。その行動療法の実際の場面も見学しましたが、感動的でした。)
その後の研究
帰国後早速アニマルセラピーを広めたいと動きを開始しました。
丁度、高齢者向けのマンションがオープンまじかだったことから、共同研究者と共に経営者と管理者に会い、話合った結果、研究プログラムに賛同してもらう事ができ研究計画を進めていました。
大きなマンションで医療施設も併設しスポーツジムや趣味の部屋などもあり、入居者は比較的自由に行動できる事もあり入り口のロビーも広くその場所なら動物(主に犬が出入りしても大丈夫だということで最適の条件だと考えて計画を進めていましたが、突然経営母体の会社が業績不振とのことで、そのマンション経営が他の会社に変わってしまいました。
その結果、新たな管理者がおせっかいはおたがいにやはり動物をマンション内に入れる事には反対とのことで計画は頓挫してしまいました。
まだまだ病院などでも動物を受け入れることが難しい時代でいろいろな衛生面やハンドラーの資格等米国の基準を取り入れて提出していたのですが認められませんでした。結局共同研究者も諦めてしまい研究は断念せざるをえませんでした。
現在では、病院や高齢者施設、子どもの療養施設など動物が介在することの効果が実証され広く受け入れられていますが、まだまだアニマルセラピーが認識されていない状況でした。
獣医学部を中心とした活動は広まりつつありましたが、一般の理解が追い付かない時代でした。
私自身も他の研究もいそがしく、教員としての仕事も多忙になり、結局アニマルセラピーを手掛けるのは私たちのバックグラウンドではそこまででした。
プライベート・アニマルセラピー
その後、私の動物、とくにアニマルセラピーへの関心は薄れたわけではなく、関心はもって過ごしていました。
世間では、動物とのかかわり方も変化し、ペット(愛玩動物)という考え方からコンパニオンアニマル(仲間としての動物)というように一部で呼び方も変わり、生活を共にする動物を家族や友人と同じように位置づける考え方に変わってきました。動物を可愛がって面倒を見るという関係から対等な関係にあり助け合って生活するという考え方です。
コンパニオンアニマルは犬や猫だけではなく、ウサギ、馬、羊、モルモット、チンチラ等多岐にわたっています。ただし、癒しの対象として位置づけられるのは犬や猫が非常に多く一般的ではあります。
我が家では子どもが小さい時からずっと大型犬と暮らしています。夫が子供の頃から犬が家族の中に居なかったことはなかったそうですが、私たちの代からでも50年は犬が一緒に暮しています。
現在の犬はイギリス系の白のゴールデンレトリバーで現在42キロの大型犬です。ゴールデンなので性格は穏やかで人が大好きです。
ですから癒しという意味では本当に癒されています。そのため、「ご家族は何人ですか?」と聞かれると「今は子どもが独立していますから3人です。我々夫婦とこの子です」とつい言ってしまいます。
アニマルセラピーが癒しを目的とするとすれば実際に我が家の愛犬はプライベート・アニマルセラピー犬ということができます。
それだけではなく、お散歩で会う方々も癒されると言ってくださる方が多いです。以前にも散歩をしていた時、前方から歩いてきた20代の若者が突然犬の前に座り、突然我が家の犬の首を抱いてしばらくじっとしていました。あっけにとられて見ているとしばらくして立ち上がり「あ~、癒された」と言って去っていきました。
散歩中に一人で散歩している女性にしばしば会うのですがその女性は会うたびに我が家の犬を可愛がってくださるので「いつも有難うございます」というと「いいえ、私が癒されているのだからお礼を言うのはこちら」とおっしゃるし、愛犬をなくした後もご自分の健康のためと毎日散歩をしていらっしゃる中高年の男性の数人も会うたびに身をかがめて我が家の犬に頬ずりしていかれます。そういう経験はほぼ毎日です。
飼い主としてはそんな様子を見るととても嬉しくなります。そしてつくづく正式ではないけれど、個人的に私たち家族だけではなく癒し効果があるセラピー犬をしているのだと思い、今になってこんな形でアニマルセラピーを実践できているような気がしています。
と書きながら、犬に興味のない方から見れば、単なる親ばか?飼い主バカ?と思われるだろうと自嘲しながら癒されているのです。
また、毎朝散歩に行くことで犬を通しての知り合いも多く、犬同士もお友達に会うことで一緒に遊んだりして楽しそうですし飼い主同士も深い関係ではないものの楽しい関係でいる事が多いです。私は「○○(我が家の犬の名前)のママ」とか「○○母さん」と呼ばれています。
お互いに立ち入ったりお節介はあまりしませんが仲良しの家で面倒を見られない日には頼まれれば代わりに餌をあげに行ったりおしっこシートの交換に行ったりして挙げていることもあり、結構助け合っています。犬のおかげで社会的関わりも増える事もあるのです。年を取ると社会と疎遠になる方も多いようですからその意味でも犬が人間関係のきっけにもなるようです。
これは大分以前から言われていますが、ペット(コンパニオンアニマル)特に散歩をする犬と生活している高齢者は飼っていない人に比べて健康寿命が長いそうですし心臓病のリスクも低いそうです。これは金魚を飼っているだけでもいくつかの病気のリスク下がるという実験結果もあります。
ヒトと動物との絆は、犬に限りませんが人間関係が希薄になりがちな現在はとても大切な気もしています。

中村延江さんの犬。
妹のららちやんと山中湖のドッグランで遊んでいるアポロです。手前の大きい方が中村さんの愛犬アポロ。

大学を定年になって以降、クリニックにいらしている方の心理療法をお引き受けして今に至り、大学院修了生の臨床実践のアドバイスも行っている。また、高齢者施設で働く介護士、ソーシャルワーカー、ヘルパーをはじめとする従業員の方々のストレス対処の相談を行っている。