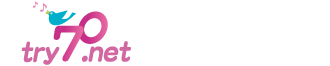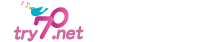伴走した1年-大谷恭子さんを悼む
伴走した1年-大谷恭子さんを悼む

満田 康子
@むらさきの縁
弁護士の大谷恭子さんと私は著者と編集者として出会った。親しくなったきっかけは紫のコート。会合が終わってエレベーターまで送っていったとき、大谷さんの手にしていた紫色のカシミアのコートに私の目は吸い付いた。むらさき談義をしてからは、一気に仲が縮まった。もう40年前のこと。
深夜12時過ぎたころ「ねえーえ」と少し甘ったれたような声で電話がかかる。音楽会へのお誘いだったり旅行のお誘いだったりする。で、当時珍しかった女性指揮者のコンサートや桜を追っかける楽しい旅も経験した。
しかし、大体は難問が持ち込まれる。
「こんなテーマで原稿を頼まれたんだけど何を書けばいいの?」
「××審議会の委員を引き受けたんだけど、詳しい学者を知らない?」
「そんなことわかるわけないじゃない」と思っても、だんだんに大谷催眠術にかけられて、「なんとか考えてみます」と答えてしまう私。という答えを引き出すまで電話を切ってくれないのだから。
けれど、私も負けていない。大谷さんが一貫して追求していた「マイノリティ」の権利についての書下ろし本を2冊依頼した。弁護士稼業のかたわら、数多くの運動体にかかわりそのリーダーを務め、大学の講義も持って、子育てもしている大谷さんに原稿を書いてもらうのは至難の業だった。
とくに東北大震災のショックは大きく、全てがむなしいと蒼白になって黙り込んだ大谷さんがなんとか気を取り直すまで説得し続けたときの困難な時間が忘れられない。
@深夜突然に
そんな繊細な大谷さんだが、国家権力と対峙するときの彼女は恐ろしく強い。
学生運動で逮捕された同志の弁護のために弁護士を志望し、刑事事件を中心に取り組んできた大谷さんである。
「もし万一、捕まることがあったら大谷弁護士を呼べというのよ。どこにいてもいつでもすぐに駆け付けるからね」。この一言が私のお守りになった。それほど危ない橋をわたってきたわけではないが、それでもやはりいつでも守ってくれる存在はなんと力強かったことか。
滅法強い彼女なのだが、暴力が大嫌いで怖がりやでもある。「拷問されたらすぐに白状しちゃうよねえ」という意気地なさがまた、私たちを結び付けたのだがーー
映画館まで行って、「え、これ、拷問場面がある!」と引き返し別の映画を見させられたこともあった。「怖い」という評判のフェミニストに会いに行くときには「ねえ、一緒に行こうよ」と強引に連れていかれた。
基本、超忙しくて超わがままな人だから、何年も音沙汰なかったりする。そしてある夜突然に、ご無沙汰の挨拶もなしに「ねえーえ」の電話がかかる。
@今回もまた、深夜に突然
ちょうど1年前もそうだった。久しぶりに会おうよと言われて会った途端に「余命宣告」を受けたという。そして「どうしても言い残したいことがあるからこれから2冊本を書く」と宣言した。
その時私が動転しなかったのは、鈍いせいもあるが、現実のことと受け止められなかったのだ。落ち着いている私を見て、勘違いした大谷さんは、「一緒にやってくれるよねえ」と言い、私はうなずいた。
しばらくは、<小春日和>が続いた。休薬期間になるとタクシーを使ってエネルギッシュに飛び回り、「病気は詐欺か」と言われると笑っていた。
私は2冊の本の順番を決めた。一番書きたいテーマを先行させて、その中でもどうしても書きたい項目から書き進めていくという戦略を立てた。ところが事態は甘くはなかった。
大谷さんは、資料を広げられるスペースのあるベッドが備わっている緩和病室に自ら希望して入った。それから1カ月、だんだん体力を失っていく大谷さんの枕もとで原稿の打ち合わせをし、若草プロジェクト(大谷さんが開いた少女のためのシェルター)の若い女性に「口述入力」をしてもらった。それをプリントアウトしてさらに補筆修正していく。健康な私でも疲れ果てる作業だったから、大谷さんはどんなに辛かっただろうか。
しみじみ静かに思い出話などまったくしないで、眉根を寄せて原稿の話ばかりしている私たちを家族の方はどう思っていただろう。今頃になって申し訳ないと思う。なにせ論文のテーマが「セックスワーク否定論」だから、乱れ飛ぶ言葉もハンパじゃない。点滴の交換に来た看護師さんがびっくりすることもしばしば。でも残されている時間はどんどん無くなる。
夜のラインの文章がだんだん短くなり、「はい」「いやだ」の返事しかこなくなり、「既読」だけがやっとつくという日々になった。
@「既読」もつかなくなって
「既読」もつかない日が何日かすぎて、論文が校正刷りになった日に、大谷さんは逝った。「必ずね、必ずね」と最後に2回念を押したのは絶対に2冊出版してねという意思だと思った。
「四十九日」に1番目の論文が出来上がってきた。そして2冊目の原稿を印刷所に入れた。
一目だけでも完成したものを見てもらって、あの美しくて人懐こい笑顔を見たかった。
大谷さんで明け、暮れた1年だった。
だが、多分私にとっても最後となる仕事を大谷さんと一緒に走れたのはとても幸せだった。
正直、新しい年の展望は全くない。